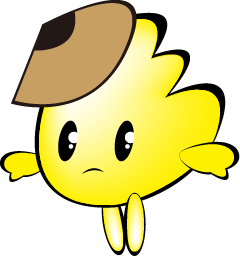JA東びわこは命を生み出す「食」や「農」の大切さを次世代へつないでいくため、「食農教育活動」に力を入れています。
私たちのエネルギー源であり、体作りに欠かせないお米について知り、学んでいきましょう!

答え合わせをしよう!キミは何問わかったかな?
解説:欠けている部分には、胚芽(はいが)と呼ばれるお米の芽(め)の部分がありました。ここから稲の根や茎が出てきます。
胚芽は、玄米を白米にする過程で、ぬかと一緒に落ちてしまいます。そのため白米の上部が少し欠けているのです。
解説:お米を研ぐ(洗う)のは、お米の表面に付いている「ぬか」や汚れを落とすためです。
現代の精米機は昔と比べて高性能です。うっすら残っている「ぬか」と、小さなゴミが入っていれば、それを洗い流すだけで良いでしょう。
解説:「無洗米」は、今まで研ぎ洗いしてい た「ぬか」をほぼ完全に除去したお米のことです。
炊く前に研ぎ洗いする必要がないので、手間や時間が掛からず便利に使える優れものです。
解説:お米は、炊くと水をたくさん吸って大きくなります。約2倍になるので、300g×2倍=600gです。
例えば4人家族で5kgのお米を買うと、茶わん約66杯分、1人当たり約16杯。1人が1日2杯食べると、お米は8日前後でなくなります。みんなの家では月にどれくらいお米を買っているかな?
解説:よく噛むことで、お米のほとんどを占める「でんぷん」が、だ液に含まれている消化酵素の働きで甘い糖に分解するため、甘く感じるのです。
よく噛むことで甘くおいしくなるだけではなく、脳や歯、胃腸の働きを良くするなどのメリットがありますよ。

解説:食事に脂質が多くなるとカロリーが高くなり、肥満を引き起こす原因につながりますが、白米そのものには油はほとんど含みません。
無理して食事を制限するのではなく、油を使った料理を減らすなどおかずの選び方に気をつけることこそが、健康的なダイエットと言えるでしょう。
解説:うるち米は、日本でもっとも食べられている、粘り気の少ない種類のお米です。
「みずかがみ」や「コシヒカリ」、「キヌヒカリ」もうるち米です。おもちを作るときには、「滋賀羽二重糯(しがはぶたえもち)」など粘り気の強いもち米を使います。インドやパキスタンの「バスマティ米」やタイの「ジャスミンライス」で知られるかおり米は、文字通り独特の香りを持っているお米で、日本でもお祭りや接待用のお米として古くから栽培されています。
解説:朝食でお米を食べると、勉強に集中する必要がある午前中、脳をイキイキとさせ、やる気や集中力を高めてくれます。
毎日の勉強は、朝ご飯がカギを握っていると言っても過言ではありません!
しっかり嚙むことで脳の血流が活発になり、より勉強に集中できますよ。
解説:大雨の時、田んぼは雨水を貯めてくれるので、川の水かさが急に増えるのを防ぎます。
普段は何気なく目にする田んぼですが、じつは大切な役割を担っているのです!田んぼに貯まった水は少しずつ流れ、一部は土の中に染み込み、地下水となり、また新たな恵みをもたらします。

解説:米を細かく砕いた米粉からは、パンやケーキ、せんべいをはじめとしたお菓子や、うどんやフォーといった麵など、色んな食品ができます。
どんな食品があるか、お店で探してみてくださいね!